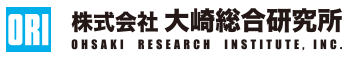活動年表
大崎総合研究所の歩みと主なできごと
| 年号 (西暦) |
社会動向 自然災害、耐震基準 |
(株)大崎総合研究所 主なできごとと研究テーマ |
|---|---|---|
| 昭和57年 (1982) |
東北新幹線・上越新幹線開通 | (株)大崎総合研究所設立 |
| 昭和58年 (1983) |
1983年日本海中部地震 三宅島噴火 |
●模擬地震波作成法の研究 ●地盤・建屋の動的相互作用の研究 |
| 昭和59年 (1984) |
1984年長野県西部地震 | ●断層モデルによる強震動評価の研究 ●確率論的地震危険度の研究 |
| 昭和60年 (1985) |
メキシコ地震 大鳴門橋完成 |
●地盤・岩盤の安定問題 ●海洋構造物と波浪の相互作用の研究 |
| 昭和61年 (1986) |
伊豆大島三原山の大噴火 | 大崎順彦社長科学技術庁長官賞受賞 ●メキシコ地震の長周期地震動解析 ●東北大学との免震構造共同研究 ●中国・工程力学研究所と共同研究 |
| 昭和62年 (1987) |
千葉県東方沖の地震 | 創立5周年記念「構造工学における先端技術と ●衝撃荷重に対するRC版の解析 ●建物周辺気流の解析 |
| 昭和63年 (1988) |
アルメニア・スピタク地震 青函トンネル、瀬戸大橋開通 |
●地震波アレー記録の解析 ●免震構造の積層ゴムの実験と解析 |
| 昭和64年 平成元年 (1989) |
米国ロマプリエタ地震 | ●関東地震の揺れの再現解析 ●埋込み基礎と地盤の相互作用実験と解析 ●浮体式海洋構造物の解析 |
| 平成2年 (1990) |
フィリピン・ルソン島地震 | ●アクティブ制振に関する実験と解析 ●地下空洞掘削時の逆解析 ●災害時避難行動シミュレーション解析 |
| 平成3年 (1991) |
雲仙普賢岳大火砕流 | ●微動アレー観測記録を用いた地盤構造の推定法 ●岩盤内浸透流の3次元解析 ●ライフラインの震災復旧解析 |
| 平成4年 (1992) |
山形新幹線開業 | 創立10周年記念「次世代建築への展望」 ●地域情報を用いた地震被害想定研究 |
| 平成5年 (1993) |
1993年釧路沖地震 1993年北海道南西沖地震 |
●構造物周りの風の3次元解析 ●3次元有効応力による液状化解析の実用化 ●オブジェクト指向による災害時避難シミュレーション解析 |
| 平成6年 (1994) |
関西国際空港開港 1994年三陸はるか沖地震 米国ノースリッジ地震 |
●釧路沖地震の大加速度記録の研究 ●3次元個別要素法による粒状体解析 ●設計支援エキスパートシステム |
| 平成7年 (1995) |
1995年兵庫県南部地震 (阪神淡路大震災) |
●兵庫県南部地震の被害調査、余震観測、観測記録・ |
| 平成8年 (1996) |
●兵庫県南部地震震災の帯の成因解明 ●構造物のヘルスモニタリング技術の研究 |
|
| 平成9年 (1997) |
長野新幹線開業 | 大崎順彦社長日本建築学会大賞受賞 ●3次元地盤構造の波動伝播解析 ●地盤・岩盤の3次元応力・浸透連成解析 |
| 平成10年 (1998) |
長野冬季オリンピック開催 明石海峡大橋開通 |
第1回和泉イブニングセミナー開催 ●断層モデルによる広帯域強震動評価手法の研究 ●地震時の家具・設備機器の挙動予測 ●次世代型構造解析システムの開発 |
| 平成11年 (1999) |
トルコ・コジャエリ地震 台湾集集地震 |
山原浩社長就任 大崎順彦会長逝去 清川哲志主席研究員科学技術庁長官賞受賞 ●関東地震による広域震度分布の解析 ●杭支持構造物の非線形地震応答解析 |
| 平成12年 (2000) |
2000年鳥取県西部地震 三宅島の火山噴火全島民避難 建築基準法及び同施行令改正(限界耐力計算法) |
●地震動強さと建物応答に関する研究 ●流体数値シミュレーション(CFD)による3次元解析 ●活断層を考慮した地震ハザードマップの作成 |
| 平成13年 (2001) |
2001年芸予地震 世界貿易センタービル崩壊 |
●愛知県設計用入力地震動策定プロジェクトの実施 ●建物内個体音伝播の予測解析 |
| 平成14年 (2002) |
創立20周年記念事業「創業二十年の歩み」出版、 ●並列コンピュータ処理による大規模計算法の検討 ●構造物の損傷モニタリングシステム |
|
| 平成15年 (2003) |
宮城県沖の地震 宮城県北部の地震 2003年十勝沖地震 |
●オフィス内地震時被害の振動台実験と解析 ●損傷モニタリングシステムの杭への適用検討 |
| 平成16年 (2004) |
2004年新潟県中越地震 スマトラ・アンダマン地震 |
●名古屋の長周期構造物設計地震動の策定 ●地震時地下水位変動予測システム |
| 平成17年 (2005) |
福岡県西方沖の地震 宮城県沖の地震 |
稲田泰夫社長就任 ●地震ハザード評価システムの高度化 ●CFDによる長大橋周りの流れ解析と最適断面の検討 |
| 平成18年 (2006) |
発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針改訂 | ●津波被害予測と避難計画システム ●断層の連動破壊に関する研究 |
| 平成19年 (2007) |
2007年能登半島地震 2007年新潟県中越沖地震 |
壇一男研究部長日本建築学会論文賞受賞 ●断層震源の動力学的破壊モデル研究 ●地震液状化による側方流動解析 ●新潟県中越沖地震の被害調査と観測記録の検討 |
| 平成20年 (2008) |
中国四川大地震 2008年岩手・宮城内陸地震 |
和泉正哲顧問日本建築学会大賞受賞 ●BCP策定支援の地震リスク評価システムの開発 ●気象モデルとCFDの組合せによる風況解析 |
| 平成21年 (2009) |
イタリア中部ラクイラ地震 駿河湾の地震 |
●孤立した短い活断層による強震動の検討 ●高精度な放射線遮蔽解析による放射線量分布解析 |
| 平成22年 (2010) |
ハイチ地震 チリ地震 |
横田治彦社長就任 ●経験式に基づく長周期地震動の予測 ●環境振動シミュレーション技術の開発 |
| 平成23年 (2011) |
ニュージーランド・クライストチャーチ地震(2月22日) 東北地方太平洋沖地震(3月11日) (東日本大震災) |
●東北地方太平洋沖地震の被害調査と地震動研究 ●長周期地震動に関する研究 ●正断層の現地調査 |
| 平成24年 (2012) |
東京スカイツリー開業 原子力規制委員会発足 |
創立30周年記念 金森博雄名誉教授講演会開催 ●プレート境界地震に伴う分岐断層の研究 ●南海トラフの巨大地震の震源モデルの設定 ●津波伝播シミュレーション解析 |
| 平成25年 (2013) |
原子力発電所の新規制基準施行 2020年オリンピック・パラリンピック東京開催決定 |
佐藤智美主席研究員日本地震工学会論文賞受賞 ●長大断層のモデル化に関する研究 ●長周期地震動作成手法の改良 ●高速鉄道トンネル内の圧縮波の伝播予測に関する研究 |
| 平成26年 (2014) |
御嶽山の噴火災害 長野県北部の地震 リニア中央新幹線着工 |
金子美香副所長日本建築学会論文賞受賞 ●断層浅部で生成される地震動に関する研究 ●津波の3次元挙動解析による荷重の算定に関する研究 |
| 平成27年 (2015) |
ネパールの地震(4月25日) 口永良部島新岳の噴火(5月29日) 小笠原沖の地震(5月30日,M8.1,深さ682Km) |
佐藤俊明社長就任 ●海溝型巨大地震の3次元断層破壊シミュレーションに関する研究 ●高速鉄道トンネル微気圧波の対策に関する研究 |
| 平成28年 (2016) |
熊本地震(4月14日,16日) 鳥取県中部の地震(10月21日) ニュージーランド南島北東部の地震(11月14日) |
●内陸地震の強震動予測手法の体系化に関する研究 |
| 平成29年 (2017) |
メキシコ沖の地震(9月8日) メキシコ中部の地震(9月19日) |
佐藤智美首席研究員日本建築学会論文賞受賞 吉田順副所長地盤工学会論文賞受賞 ●熊本地震による断層ごく近傍の永久変位に関する研究 ●巨大海溝型地震の設計用長周期地震動の検討 |
| 平成30年 (2018) |
台湾花蓮の地震(2月6日) 大阪府北部の地震(6月18日) 西日本の豪雨災害(平成30年7月豪雨) 北海道胆振東部地震(9月6日) |
●強震動予測のための長大断層のパラメータ設定方法 ●南海トラフの地震に対する設計用入力地震動 |
| 平成31年 令和元年 (2019) |
2019年ペルー地震 令和元年台風15号 令和元年台風19号 |
●断層極近傍の地震動に係る浅部断層破壊の研究 ●城郭石垣の調査・安定性評価 ●風力発電の普及に向けての活動 |
| 令和2年 (2020) |
令和2年7月豪雨(熊本県他) | ●2016年熊本地震震源近傍での非線形地盤震動解析 ●「伊方SSHACプロジェクト」への参画 ●高速鉄道トンネル内の圧力変動履歴の予測 ●UAVを用いた大型PC橋梁の点検用3Dモデルの構築 |
令和3年 (2021) |
令和3年8月の大雨 | ●地震波を用いた各種の逆解析(インバージョン)手法による広帯域の断層破壊過程の解析 ●震源断層モデルの設定のための短周期レベルの再構築 ●プログラムソースの公開 ●「富岳」成果創出加速プログラムへの参画 |
令和4年 (2022) |
創立40周年記念講演会・懇親会開催 ●震源断層モデルの設定方法の高度化の検討 ●最大加速度の確率論的地震ハザード評価 ●高速鉄道トンネル内分岐通過で発生する圧力波の抑制 |
令和5年 (2023) |
令和5年奥能登地震(5月5日) | ●レジリエンス&サステナビリティを考慮した建物性能評価の体系化を目指した産学共同研究 ●SIPスマートインフラマネジメントにおける「地域インフラ群のマネジメント技術」の研究 ●M9クラスの海溝型プレート間地震の特性化震源モデルの構築 |
令和6年 (2024) |
令和6年能登半島地震(1月1日) | ●令和6年能登半島地震の震源モデルの検討 ●第3期戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)「スマートインフラマネジメントシステムの構築」への参画 ●城郭石垣の地震時安定性検討に対する取り組み |
令和7年 (2025) |
野澤剛二郎社長就任 |